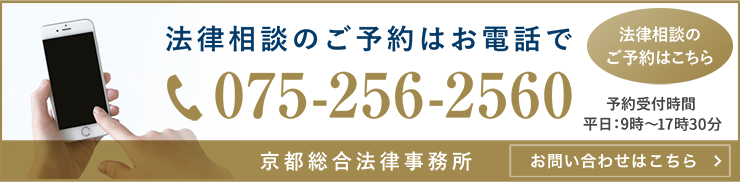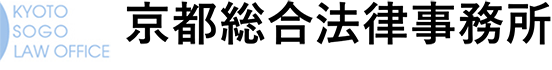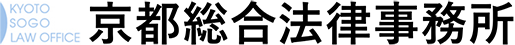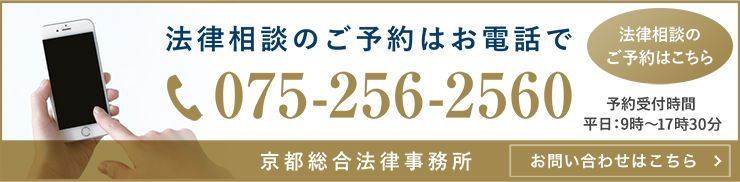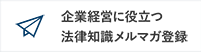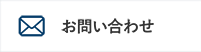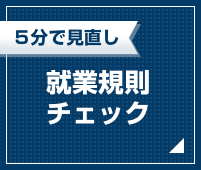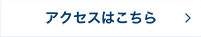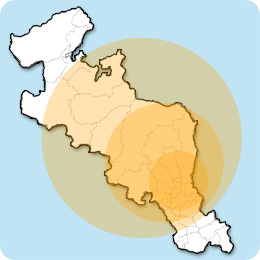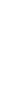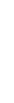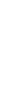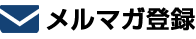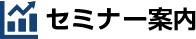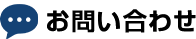不動産売買における弁護士の役割と相談のポイント

目次
1.不動産売買に関連する主なトラブルで弁護士に依頼すべきケース
(1)売買代金の未払い、物件の引渡拒否などの契約不履行
不動産売買契約を締結しているにもかかわらず、買主が売買代金の支払いを遅延または一切行わないケース、売主が物件の引渡しに応じないケースがあります。このような契約不履行状態が長期化すると、損害賠償の請求や契約の解除といった大きな問題への対応を余儀なくされる可能性が高まります。
早期かつ継続的に弁護士に相談することで、見通しを立て、内容証明郵便を使った請求や必要に応じた法的手続き(保全や訴訟等)を適時に適切に行うことで、早期の解決や損失の最小化を図ることが期待できます。
(2)境界線を巡る紛争や越境トラブルが避けられない場合
隣接する土地との境界が不明確なまま売買を進めると、買主や近隣住民とのトラブルが後々に表面化するリスクがあります。たとえば、「塀や建物の一部が隣の敷地に越境していた」「境界線が記載された公図と現状が一致しない」といったケースです。
境界を確定させてから売買するのが望ましいですが、そのためにどのように交渉すれば良いか悩ましいという場面もあります。弁護士は、境界に関する専門家(土地家屋調査士・測量士等)と連携し、交渉の段階から法的視点を踏まえてアドバイスを行うことで、無用な紛争の発生を未然に防ぎます。
(3)道路の通行を巡るトラブルがあり得る場合
道路の所有者が他人の名義である場合、いざ建物を建てようとすると私有地の所有者が工事車両の通行を拒否してきたり、もっと厳しいケースですと日常の車両の通行を拒否してきたりするケースも散見されます。
弁護士は、道路の通行に関する様々な判例・裁判例を踏まえて、通行に関するアドバイスを行いますので、適切な見通しに基づいた土地の利用方法を検討することがきます。
(4)相続や共有状態で権利関係が複雑な不動産を利活用する際
相続人が多数いる、あるいは複数人が共有名義で不動産を持っている場合、誰がどの割合で権利を有しているかを整理しなければ売買等の利活用ができません。共有者の一部が協力的でない、相続人が行方不明など、話し合いが難航するケースでは、調停や訴訟が必要になることもしばしばあります。
弁護士であれば、他の共有者との交渉や調停や裁判を代理することで、売買等の利活用を妨げる根本的な原因の除去をサポートすることができます。
(5)契約不適合が見つかった物件で修繕費や責任範囲をめぐる交渉が必要な場合
雨漏りやシロアリ被害、構造上の欠陥など、外からは分かりにくい欠陥(契約不適合)が契約後に発覚することがあります。そのような紛争では契約不適合責任の範囲や期間が問題となり、売主・買主双方の意見が激しく対立します。
弁護士は、物件の調査結果に基づいて責任の所在や修繕費の負担割合を明確にし、双方の合意が得られる着地点を探る交渉を円滑に進めます。
(6)抵当権や賃借権が設定された不動産を売買する場合
不動産に抵当権(ローンの担保)や賃借権(テナントが入居しているなど)が付着している場合、その処理を誤ると買主が想定した使用収益ができなくなる可能性が生じます。
弁護士は、担保の処理方法、賃借権への対応方法、引渡し後のリスク等を検討し、具体的な解決策を提示します。
もちろん弁護士はトラブルに対して精一杯対応しますので、トラブル時に心強い存在ですが、そもそも売買時にきちんとチェックできていれば慌てることはありません。「こんなはずではなかった」と後悔しないためにも、事前にご相談いただければより安全により安い解決が可能となります。
2.不動産売買契約で弁護士がサポートできること
(1)契約書類の作成およびチェック
不動産売買契約書は、売買価格や物件の引渡条件、違約金の取り扱いなどを細かく取り決める非常に重要な書面です。弁護士が作成や内容チェックを行うことで、契約違反があった際の救済策や、それぞれのリスク分担などを的確に盛り込むことができます。特に高額な物件や特殊な要件(古家付き土地など)が絡む場合は、弁護士の知見を活用して見落としを防ぎましょう。
(2)売買価格や特約条項に関する交渉代理
不動産の売買価格は、単に相場や査定額だけで決まるわけではなく、瑕疵や権利関係の複雑さなどを踏まえた「交渉」がカギとなる場合があります。また、契約解除の条件や瑕疵担保責任の期間・範囲、引渡し後の設備修理負担など、多岐にわたる特約事項をどう定めるかによって、トラブルが起こりにくい契約が組めるかが左右されます。弁護士は依頼者の利益を最大限に確保しつつ、合理的な解決へ導くサポートを提供します。
(3)物件の権利関係とリスクの詳細調査
売買対象となる不動産が、登記上は単純な所有権移転で済む物件なのか、それとも抵当権や第三者の権利が存在しているのかを正確に調査することは非常に重要です。権利関係が不明確なまま契約を結ぶと、取引後に大きな紛争へ発展する可能性があります。弁護士は登記や権利証の確認だけでなく、必要に応じて関係者へのヒアリングや追加資料の収集を行い、リスクを洗い出します。
(4)訴訟・調停・仲裁手続きの代理人としての活動
不動産売買でトラブルが生じ、交渉や話し合いでは解決が難しい場合、裁判所を通した調停や訴訟へ進むこともあります。弁護士は、訴状や答弁書の作成、証拠の収集と提出、裁判所での主張立証といった一連の手続きを担当します。また、裁判手続き以外にも、仲裁・あっせん等民事上の紛争解決手段を駆使して依頼者の利益を守ります。
(5)契約不履行時の損害賠償請求や強制執行の支援
売主・買主いずれかが契約条件を守らなかった場合、損害賠償の交渉や強制執行(財産の差押え等)を行うことで権利を実現することが必要になります。弁護士は、依頼者が被った損害額を明確化しつつ、交渉による早期解決や裁判手続きの選択など、最適な手段の検討から実行までをサポートします。結果的に依頼者が受ける負担を軽減し、スムーズに問題解決を目指せるよう尽力します。
3.不動産売買による弁護士の解決事例
【不動産の二重譲渡が懸念されたケースで、保全と裁判を駆使して解決した事例】
XがYから不動産を買うということで売買契約を締結しました。しかし、決済日が近づいているのにYとの間で決済についての話が前に進みません。
不審に思ったXは、顧問弁護士である我々に相談しました。
我々は、Yの挙動から二重譲渡を計画しているのではないかと察知しました。
そこからは時間勝負です。手をこまねいているうちに二重譲渡され、登記を移転されてしまったらどうしようもありません。そこで、直ちに売買目的不動産を保全(仮処分)し、まずは売買目的不動産をロックしました。
無事保全できましたので、その後は落ち着いてYを訴え、最終的に裁判上での和解により解決を図ることができました。
【契約不適合】
XがZから購入し、Yに売却した土地に廃棄物が埋まっていました。YはXに対し、廃棄物の撤去費用や土壌の入れ替え費用等を上乗せて請求し、裁判になりました。Xの仕入れ値は1000万円で、Yへの売却代金は2000万円ですが、YからXへの請求額は5000万円でした。
裁判では、一審はYの請求を認めてXに5000万円の支払いを命じましたが、さすがにそれは酷いということで控訴し、控訴審で新たな切り口から主張立証を追加した結果、控訴審では売却代金ベースで和解することができました。
4.弁護士の必要性
不動産売買においては、不動産仲介業者や司法書士だけで対応しているケースも多々あります。しかし、物件が高額であったり、特殊な用途が想定されていたり、あるいはすでに契約不履行や瑕疵トラブルの兆しが見えている場合は、弁護士への相談が極めて重要です。なぜなら、法的リスクを正確に把握し、早期に対策を講じることで、長期化する紛争や多額の損害賠償を回避しやすくなるからです。
たとえば、共有者が多数いる不動産の売却や、相続で権利関係が錯綜している物件の処分などは、書類確認だけでは不十分な局面が多く、弁護士が問題点を整理しながら必要に応じて他の専門家と連携することで、取引を安全に進める道筋を見出せます。
また、訴訟に発展することも見据え、書類や証拠の収集、裁判外の交渉等を戦略的に動くこともできます。
さらに、外国人名義の不動産売却や、企業同士の大規模な事業用地取引など、近年は一般の方には扱いづらい複雑なケースが増えています。
弁護士はこうした多様化するニーズにも対応し、関連する法的規制や税制面の注意点などを踏まえて包括的なアドバイスを行います。大切なのは「問題が起きてから」ではなく「問題が起きる前に」法的視点を取り入れておくことです。わずかな疑問点でも放置すると、大きなリスクにつながる可能性があります。
5.当事務所のサポート内容
<スポットでのご対応>
経済的利益、つまり、私たちに解決をご依頼いただくことで得ようとする(または排除しようとする)金額を基準とし、下記の表によって算出させていただきます。
| 経済的利益 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万以下の場合 | 8% | 16% |
| 300万を超え3000万以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万を超え3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
たとえば、300万円の債権の回収の場合、着手金(ご依頼時にお支払いいただく費用)と報酬金(解決時にお支払いいただく費用)は次のとおりとなります(実費は別途ご負担いただきます)。
着手金 24万円+消費税額
報酬金 48万円+消費税額
<継続的なご対応>
私たちは、弁護士と皆様とが継続的な信頼関係を築くことで、より深く、より手厚いリーガルサポートを行いたいと考えています。
従来の顧問契約のイメージから一歩進み、皆様の実情を積極的に理解し、適切な対応を瞬時に行う。
それが私たちの法律顧問サービスの特長であり信念です。
当事務所のリーガルサポートプランには、
✅それぞれが専門分野を持ったパートナー弁護士全員が企業活動を総合的かつ多角的にサポート
✅案件に応じて適切な弁護士がアサインすることで全ての案件にベストな解決をご提案
✅サポートする弁護士が増えても月額料金は同じ
という特長があり、予防法務はもちろん戦略法務の観点からも幅広くご利用いただいています。
リーガルサポートプランの具体的な内容は次の表のとおりです。
| 京都総合法律事務所 リーガルサポートプランのご案内 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 月額ご利用料金 (税別) | 5万円 | 10万円 | 15万円 | |
| 1 | ホームページ等への弁護士表示 | ○ | ○ | ○ |
| 2 | 原則24時間以内の応答 (事務所休業日を除く) |
○ | ○ | ○ |
| 3 | 相談予約の優先対応 | ○ | ○ | ○ |
| 4 | ワンストップサービス | ○ | ○ | ○ |
| 5 | 事務所での相談 | ○ (月4時間程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
| 6 | 電話相談 | ○ (月2時間程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
| 7 | メール相談 | ○ (月2案件程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
| 8 | チャット相談 | ○ (月4案件程度) *2 |
○ (無制限) |
○ (無制限) |
| 9 | 時間外電話相談 *1 | × | ○ (月4回程度) |
○ (無制限) |
| 10 | 出張相談 | × | ○ (月1回程度) |
○ (月2回程度) |
| 11 | 契約書や社内規定のリーガルチェック | × | ○ (高難度等は除く) *3 |
○ (無制限) |
| 12 | EAP | × | ○ | ○ |
| 13 | 社内研修講師 | × | ○ (年1回程度) |
○ (年3回程度) |
| 14 | 社内会議への参加 | × | × | ○ (月1回程度) |
| 15 | 個別事件の弁護士費用割引 | 5%OFF | 10%OFF | 15%OFF |
※1 時間外とは、平日9:00~17:30以外の時間及び土日祝です。
※2 事務所での相談、電話相談、メール相談、チャット相談を合計して月4時間程度を上限とします。
※3 高難度等とは、専門的・先端的分野又は5ページ以上の内容を目安とします。
※4 上記は標準的なプランの内容を示しており、実情に応じてカスタマイズいたします。
ご相談・お問い合わせは以下のフォームからご入力またはお電話ください。
関連ページ
▶賃料回収