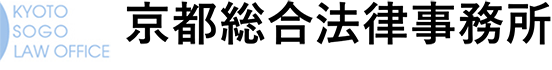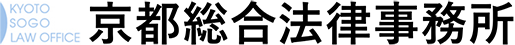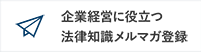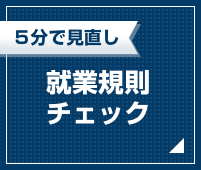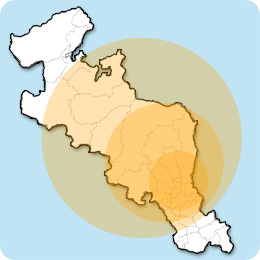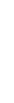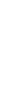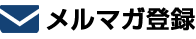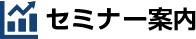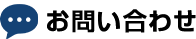【判例解説】新聞記事の著作物性 ~つくばエクスプレス事件~

裁判例①:知財高判令和5年6月8日(令和5年(ネ)第10008号)(一審原告:㈱日本経済新聞社)
裁判例②:知財高判令和5年6月8日(令和4年(ネ)第10106号)(一審原告:㈱中日新聞社)
上記の裁判例①②は、新聞記事を撮影して社内ネットワーク上にアップロード等して従業員等が見られるようにしていた行為が著作権侵害にあたるとして、大手新聞社2社からの損害賠償請求がなされた事案です。
結論としては、第1審及び控訴審のいずれにおいても、問題となった新聞記事は著作物にあたると判断され、控訴審においては①事件で約700万円、②事件で約130万円の損害賠償請求が認められました。
報道は企業の経済活動にとっても必要性が高いため、自社の業務分野に関係のある報道等を社内で周知・共有するために、社内で複製したり、社内ネットワークにアップロードしたりしている企業も多いのではないでしょうか。
しかし、本裁判例①②が示したように、新聞記事に著作物性が認められ、新聞記事の画像データの複製・アップロード等が損害賠償請求の対象になる場合があるので、注意が必要です。
この記事では、①②の裁判例がどんな点に着目して著作物性を認めたのかなど、新聞記事の著作物性についてご説明します。
1 新聞記事の著作物性
著作権法10条2項は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は…著作物に該当しない」と定めています。そうすると、事実を報道する新聞記事は著作物にあたらないとも思えます。
確かに、事実を端的にわかりやすく伝える必要がある報道においては、伝達者が行う表現上の工夫の幅は限られ、創作的表現を保護する著作権法においては保護されないとも思われます。
例えば、「だれだれが何々をした」や、「いつどこで何々が起きた」という誰が書いても同じような表現になる簡潔な事実の伝達のみであれば、作成者の表現上の工夫、すなわち創作性が認められず、著作物にあたらないと考えられます。
そこで、同項は、単なる事実の伝達にすぎない報道等については、創作性が認められないことを確認的に定めたものです。
この点、東京地判昭和47年10月11日判タ289号377頁は、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とは、単なる日々の社会事象そのままの報道記事をいう旨判示しています。
また、知財高判平20・7・17判時2011号137頁(ライブドア裁判傍聴記事件)では、ライブドア裁判の傍聴ノートをインターネットで公開したところ、他人が無断でブログに掲載した事例につき、
「言語表現による記述等における表現の内容が、専ら『事実』(この場合における『事実』とは、特定の状況、態様ないし存否等を指すものであって、例えば『誰がいつどこでどのようなことを行った』、『ある物が存在する』、『ある物の態様がどのようなものである』ということを指す)を、格別の評価、意見を入れることなく、そのまま叙述する場合は、記述者の『思想又は感情』を表現したことにならないというべきである(著作権法10条2項参照)」
旨判示しています。
もっとも、実際の新聞記事では、単なる社会事業そのままの報道記事ではなく、分かりやすく伝わりやすい報道になるよう、様々な工夫等がされていることも多く、そこに作者の個性が現れているといえる場合には単なる事実の伝達ではないとして、著作物性が認められ得るのです。
では、どのような工夫がなされた新聞記事であれば、著作物にあたるのでしょうか。本裁判例①②の判示を見てみましょう。
2 本裁判例①②の判断
新聞記事の著作物性について、裁判例①の控訴審においては、
|
「一審被告は、本件各記事が事実を伝達するものにすぎず、文章表現もありふれているなどとして著作物性を否定する旨の主張をするが、本件各記事において、記事内容を分かりやすく要約したタイトルが付され、文章表現の方法等について表現上の工夫が凝らされていることは原判決認定のとおりである(原判決第3の2⑴)。」 「同記事は、同日(平成31年3月28日)に掲載された他社記事と比較して、東急電鉄の発祥や設立経緯についての記載はなく、かえって商号変更の理由が分社化に伴うものであることを記載するなど、記載内容の取捨選択がされ、記者の何らかの創造性が顕れており、著作物であると認められる。本件各記事は、法10条2項にいう「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」とはいえないから、一審被告の上記主張は採用することができない。」 |
と判示されています。
そして、上記控訴審の判示で引用された裁判例①の原判決第3の2⑴においては、
| 「本件各記事は、いずれも、担当記者が、その取材結果に基づき、記事内容を分かりやすく要約したタイトルを付し、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係を端的に記述すると共に、関連する事項として盛り込むべき事項の選択、記事の展開の仕方、文章表現の方法等についても、各記者の表現上の工夫を凝らして作成したものであることがうかがわれる。」 |
と判示されています。
また、裁判例②の控訴審においては、
| 事故に関する記事や、新しい機器やシステムの導入、物品販売、施策の紹介、イベントや企画の紹介、事業等に関する計画、駅の名称、列車接近メロディー、制服の変更等の出来事に関する記事であるところ、そのうち、事故に関する記事については、相当量の情報について、読者に分かりやすく伝わるよう、順序等を整えて記載されるなど表現上の工夫をし、それ以外の記事については、いずれも、当該記事のテーマに関する直接的な事実関係に加えて、当該テーマに関連する相当数の事項を適宜の順序、形式で記事に組み合わせたり、関係者のインタビューや供述等を、適宜、取捨選択したり要約するなどの表現上の工夫をして記事を作成していることが認められ、各記事の作成者の個性が表れており、いずれも作成者の思想又は感情が創作的に表現されたものと認められるものであり、「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道」であるということはできない。また、著作物といえるための創作性の程度については、高度な芸術性や独創性まで要するものではなく、作成者の何らかの個性が発揮されていれば足り、報道を目的とする新聞記事であるからといって、そのような意味での創作性を有し得ないということにはならない |
と判示されています。
したがって、タイトルの要約の仕方の工夫、直接的に関係のない事実関係を選択し、盛り込んだ点、記事の展開の仕方、文章表現の方法等について工夫がなされており、作者の個性が発揮されているといえる場合には、新聞記事に著作物性が認められるといえます。
3 関連裁判例
労働組合の機関誌の著作物性が認められた事例
(福岡地大牟田支判昭59・9・28無体裁集16巻3号705頁(日刊情報事件))
労働組合によって発行された機関紙について、労働組合としての闘争を前進させるための情勢分析、闘争方針や要求を記事に盛り込んだものであり、事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道に該当するとは認められず、思想または感情を創作的に表現したもので学術の範囲に属するものに準ずるものとして著作物性を認めた。
インターネットニュース記事の見出しの著作物性が否定された事例
(ヨミウリ・オンライン事件(東京地判平16年3月24日判時1857号108頁))
見出しは簡潔な表現であり、多くは20字未満で表現の選択の幅が広いとは言えないこと、記事中の言葉をそのまま用いたりこれを短縮した表現やごく短い修飾語を付加したものにすぎないこと等から著作物性が否定された。
(なお、控訴審においても見出しの著作物性は否定されたものの、多大な労力、費用をかけて作成された見出しは法的保護に値する利益であるとして、不法行為に基づく損害賠償請求は一定額認められています。)
4 まとめ
裁判例①②及び上記の関連裁判例を踏まえると、端的に社会事象を述べる、すなわち5W1Hを伝えるだけの短い記事ではなく、事実をわかりやすく伝えるための様々な工夫がなされている新聞記事であれば、著作物性が認められることが十分にあり得ると考えられます。
著作物性が認められるには「創作性」が必要ですが、これは高度な芸術性等を要求するものではなく、作者の何らかの個性が表現されていて、ありふれた表現でもなければ、創作性が認められるというのが、著作権法の基本的な考え方です。したがって、フィクションのように0から作った独創的なものではなく事実に基づく新聞記事についても、創作性が認められ得るのです。
冒頭に述べたように、新聞記事を社内でコピー・アップロード等する必要のある企業も多いかと思いますが、本件のように継続的・習慣的に行った場合、損害賠償として数百万円を支払うことになる可能性もあります。
なお、裁判例①②において、損害額(著作権法114条3項)は、新聞記事1記事あたり5000円で算定され、裁判例①においては1266件、裁判例②においては232件の新聞記事の著作権侵害が認められました。
そのため、新聞記事を共有する場合には、発行元に許諾を得るか(大手各社の新聞記事の一定の範囲でのコピーやPDF化について包括的な年間契約をすることも可能のようです。(参考:新聞著作権協議会 「新聞著作権協議会とは?」)、作者の創意工夫が現れた表現をそのまま複製・アップロードしないように、事実だけを端的に要約して共有するなどして、著作権を侵害しないよう注意する必要があります。
著作権侵害にあたるかは、具体的な新聞記事の内容や共有方法等にもよりますので、ご心配があれば、一度ご相談いただければと思います。
執筆者:弁護士 小山田桃々子
5 関連ページ
著作権に関する記事はこちら
著作権に関連する事例はこちら
・【弁護士による判例解説】生徒の演奏も著作権侵害? -音楽教室訴訟控訴審判決-
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。