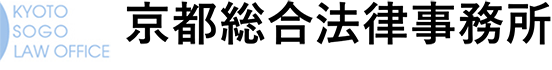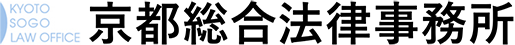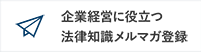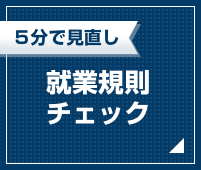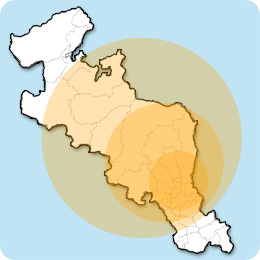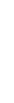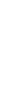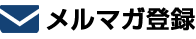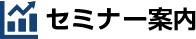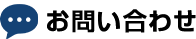【弁護士による判例解説】契約社員に退職金を支給しないこと等が不合理ではないとされた事例(最判令和2年10月13日―メトロコマース事件)

事案の概要
Xさんらは、M社で売店販売業務にあたる契約社員として、1年間の契約期間を更新しながら、65歳になるまで10年以上、働き続けました。
M社の正社員は、65歳で定年となり、定年退職時には退職金の支給がなされていましたが、契約社員であるXさんらには、退職金の支給がありませんでした。
そこでXさんらは、契約社員に退職金が支給されないのは、雇用期間に相違があることのみをもって、労働条件に不合理な区別を設けることを禁止した法律の定めに反するとして、M社に対し、損害賠償請求をしました。
最高裁判例の概要
Xさんらに退職金が支給されないことは、次のような事情を考慮すると、不合理な区別にはあたらないとしました(判決文そのままの表現ではありません)。
① 退職金の支給の有無が不合理かどうかは、退職金の性質やこれを支給することとされた目的をふまえて、職務の内容(業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度)やその職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して判断すべきである。
② M社の退職金は、職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有しており、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対して支給されるものと評価できる。
③ 売店販売業務にあたるM社の従業員の業務内容は、Xさんらと正社員とで概ね共通ではある。しかし、欠員が生じた際の代務業務、統括・指導・改善等の業務など、責任の度合いに一定の相違があり、また配置転換等の有無など配置の変更の範囲にも相違があった。
判決のポイント
今回示された最高裁の判断では、売店業務という点では、同じ仕事であるといえそうな正社員と契約社員であっても、責任の重さや人材活用の仕組みが違うことが具体的に検討された結果、職務の内容や人材活用の仕組みが違っているとされました。
ただ、そういう違いがあったとしても、退職金の性質を給料の後払い的なものであると理解すれば、正社員と同額とはいかないものの、契約社員にも一定程度の退職金は支払わなければならないのでは、という疑問が生じ得ます。しかし今回の最高裁の考え方では、M社の退職金には、正社員としての職務を担うのにふさわしい人材確保・定着目的も複合的に含まれるとして、特に正社員だけに退職金を支払うという方法も不合理ではないとされました。
飲食業や小売業などでは、正社員と契約社員とが同じ職場で同じように働くというケースが少なくありません。多くの場合、店長職のように責任ある仕事を任されるのは正社員であり、今回の最高裁の判断は、こうした責任の度合いの違いに着目したものといえます。
もし、契約社員にも正社員並の責任を課していたり、様々な職務を兼任させているような場合には、この最高裁の判断があるからといって、退職金を支給しないことが損害賠償の対象となり得るリスクを伴います。
今回のケースでも、契約社員とはいえ、契約更新によって正社員よりも長期間働く場合があり得たことや、60歳を超えての正社員登用もあったという実情があり、このことを考えると、こういう立場にある契約社員との関係では、退職金の功労報酬としての性質は当てはまるのではないか、という疑問があり得ます。
また、統括・指導・改善等のいわゆるマネージャー業務が他の売店業務と質的に異なるといえるか、評価が分かれ得る点です。今回の最高裁判決には、このような観点から、契約社員と正社員との間で責任の度合いや人材活用の仕組みに大きな相違はないとした反対意見が付されており、契約社員には退職金を支給する必要がないと形式的に割り切ることことは禁物です。
契約社員に退職金を支給しないという仕組みを採用しておられる場合、正社員との待遇差を合理的なものといえるだけの責任の度合いや人材活用の仕組みに違いがあるといえるかどうか、是非とも弁護士のアドバイスをお受けください。
関連ページ
▶労働審判
▶労働訴訟
京都総合法律事務所は、1976(昭和51)年の開所以来、京都で最初の「総合法律事務所」として、個人の皆さまからはもちろん、数多くの企業の皆さまからの幅広い分野にわたるご相談やご依頼に対応して参りました。経験豊富なベテランから元気あふれる若手まで総勢10名超の弁護士体制で、それぞれの持ち味を活かしたサポートをご提供いたします。